医療栄養学科

大腸癌は部位別で最も罹患率が高く、増加傾向にあり、再発率も高く、さらに術後にQOLの大きな低下を伴います。したがって、大腸癌の予防戦略を確立することは緊急かつ非常に重要な課題です。大腸癌の罹患率には国レベルで顕著な地域差があります。これは食生活の違いによって説明することができます。しかし、食事に含まれる栄養素のほとんどは小腸で吸収されるため大腸には流れ込みません。肝臓で合成され腸管に分泌される胆汁酸も多くは小腸で再吸収されますが、一部は大腸へ流入し、さらに腸内細菌によって発癌性の二次胆汁酸に代謝されます。胆汁酸は食事と大腸癌のリスクの関係を説明する有力な候補として考えられています。そこで私たちは、腸管内胆汁酸代謝に影響を及ぼす食事性因子を明らかにすることにより、大腸がんの発症・再発予防戦略を構築することを目指しています。
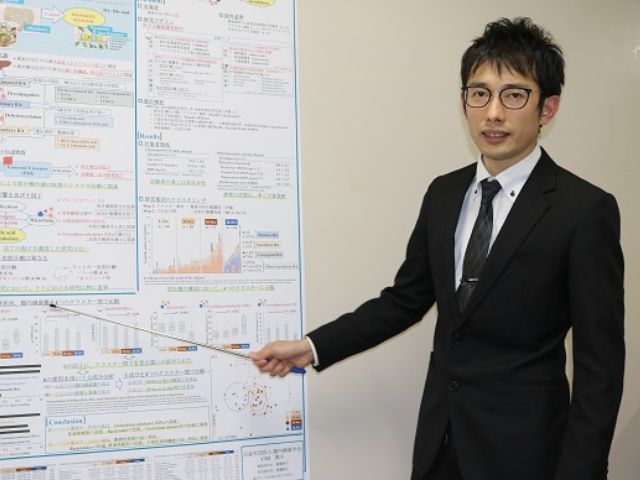
2020年に行った調査で、大きな発見がありました。約70人の健康な人たちの胆汁酸の排泄状況、食事内容、腸内細菌の働きを調べたところ、胆汁酸の排泄量が多い人と少ない人では50倍の差があり、動物性脂質の高い摂取と不溶性食物繊維の低い摂取の組み合わせで、糞便中の二次胆汁酸濃度が高まる可能性が示唆されました。しかし、脂質と食物繊維は摂取源(例:肉の脂と魚の脂、穀類の食物繊維とイモ類の食物繊維)によって腸管内BA代謝への影響は異なる可能性があります。したがって、栄養素ベースではなく食品ベースでさらなる解析を行いました。結果として、葉物野菜や根菜類の摂取が、一次胆汁酸から二次胆汁酸への微生物変換に影響を与える可能性が示唆されました。さらに、エネルギー摂取源を洋菓子、豚肉、牛肉、卵などの脂肪の多い食品から米などの低脂肪穀類にシフトすることで、糞便中の二次胆汁酸が低下する可能性が示唆されました。
予想外なことに、ヒト肝臓で合成される一次胆汁酸を高く排泄している人が一定数存在していました。これは、胆汁酸のもとになるコレステロールが体外に出ているという証拠で、突き詰めれば、高コレステロール血症などの病気の治療につながるかもしれません。一次胆汁酸を優位に排泄した人は、他の二次胆汁酸を優位に排泄した人とは明らかに異なる腸内細菌叢を有していました。
この他、「日本人の減塩を促進する戦略提案」「リンを過剰摂取する若者への警鐘」などの研究を行っています。自身の研究の意義は「管理栄養士にエビデンスを与えること」にあります。患者さんに説得力のある栄養指導を行ってもらうために、科学的な根拠を示すのが私の役目であり、現場で生きる研究をこれからも続けていきたいと考えています。
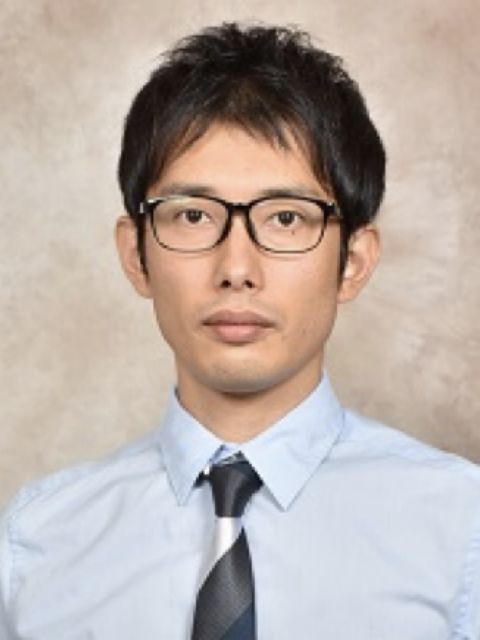
齋藤 瑛介(さいとう ようすけ)
広島国際大学 健康科学部 医療栄養学科 講師これまでの掲載記事