医療栄養学科
いのちを学び、専門性を養う。
「食」は、いのちの源となる大事なもの。疾病予防、介護予防、病気の重症化予防など、健康維持に深くかかわっています。 一人ひとりの生活やこころの状態などを踏まえ、適した栄養指導ができる管理栄養士をめざして、基礎から段階的に学修。実践する力を養っていきます。
1年次基礎を固める
「管理栄養士」の役割や使命を学び、将来像を固めていく
化学・生物の補習教育を行い、基礎を徹底的に固めます。同時に実習・実験科目もスタート。管理栄養士としての自覚を育みます。
カリキュラム
スタンダード科目
(1年次)
オプション科目
(1〜3年次)
専門教育科目
(1年次)
医療人養成に向けた基礎教育
社会・環境と健康
人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
食べ物と健康
基礎栄養学
栄養教育論
スポーツ栄養分野
まなびと連動した学外との連携
関連科目
※ ■は必修科目※カリキュラムは予定であり、変更になる可能性があります。
2年次専門性を深める
段階的な教育プログラムを通して、専門知識を身に付ける
専門的科目が増加。段階を踏んで積み上げていく体系的な教育プログラムで、学んだ専門知識を実践する力へと結び付けていきます。
カリキュラム
スタンダード科目
(2〜4年次)
オプション科目
(2〜3年次)
専門教育科目
(2年次)
社会・環境と健康
人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
食べ物と健康
基礎栄養学
応用栄養学
栄養教育論
臨床栄養学
給食経営管理論
スポーツ栄養分野
まなびと連動した学外との連携
※ ■は必修科目 ※カリキュラムは予定であり、変更になる可能性があります。
3年次現場感覚を養う
さまざまな実習を経験し、現場で対応できる力を養う
実践的な学修が中心となる3年次。学内外で行うさまざまな実習を通して、管理栄養士としての専門性、現場対応力を高めていきます。
カリキュラム
スタンダード科目
(3年次)
専門教育科目
(3年次)
人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
食べ物と健康
応用栄養学
臨床栄養学
公衆栄養学
給食経営管理論
スポーツ栄養分野
医療栄養分野
まなびと連動した学外との連携
関連科目
※ ■は必修科目 ※カリキュラムは予定であり、変更になる可能性があります。
4年次国家試験に挑む
管理栄養士の国家試験合格へ向けた、総仕上げ
それぞれの研究室で、卒業研究を進めます。卒業論文の発表後は、本学独自の国家試験対策プログラムに集中し、合格をめざします。
カリキュラム
専門教育科目
(4年次)
※ ■は必修科目 ※◆は選択必修科目 ※カリキュラムは予定であり、変更になる可能性があります。
授業科目紹介
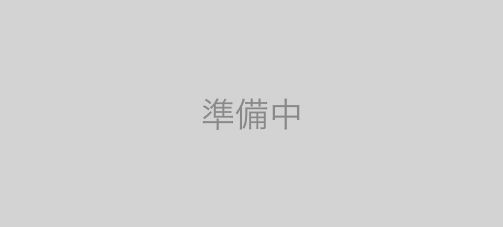
食べ物と健康
食品は衛生面や栄養面のみならず、健康に寄与する機能性も付加されています。加工原理を学び、科学的な根拠に基づいた食品加工の知識を習得します。(坂本 宏司教授)
受講した学生の声


基礎栄養学
生体は摂取した栄養素をエネルギーへ変換し、さらに生体構成成分を合成し、生命を維持しています。実験を通して、生体内での栄養学的機能について理解します。(岡村 友理香助教)
受講した学生の声


応用栄養学
各ライフステージに適した栄養ケアマネジメントについて学びます。妊娠期から出生後、乳児期、幼児期、成長期、成人期、高齢期に至るまでの栄養アセスメントや栄養ケア計画の立案を行います。(中村 亜紀教授)

栄養教育論
教育内容に聞き手の年齢や理解度に配慮した工夫を加え、栄養教育を受けた人がすぐにでも実践したくなるような教育プログラムを完成させて発表します。(山口 光枝教授)
受講した学生の声


臨床栄養学
疾病や障害を有する人の食事・栄養摂取の方法について学びます。事例を挙げて、ディスカッションを重ねながら、傷病者に適切な食事・栄養摂取について提案できる力を養います。(齋藤瑛介講師)
受講した学生の声


公衆栄養学
地域で生活する人々の健康・栄養状態をよくするために管理栄養士としてどのように活動すればよいか、実際の課題分析や計画づくりを通して学びます。(森 宏子講師)
受講した学生の声


給食経営管理論
利用者のニーズに合った献立作成を行い、原価管理、衛生管理、生産管理など給食経営管理の一連をグループで実施し、大量調理の特徴を理解します。(木村 留美准教授)
受講した学生の声


スポーツ栄養分野
本学科が連携しているスポーツ団体の選手に対して食事調査等を実施し、その結果をもとに栄養セミナーや個別栄養教育のシミュレーションを行います。(梶井 里恵講師)
受講した学生の声

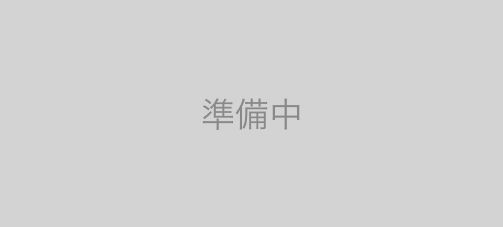
医療栄養分野
専門職連携総合演習は、広島国際大学全学科共通で実施する科目です。11学科混合で約60のチームに分かれ、提示された症例患者に必要なケアについて、話し合い、検討しあう科目です。(齋藤 瑛介講師)
受講した学生の声


まなびと連動した学外との連携
学外の企業等と連携し、スーパーのレシピカードの作成や保育園での読み聞かせ、カフェメニューの作成、広島食材の魅力発信についての企画・提案を行います。学内での学びを基に、さまざまな体験を通して地域の食育に貢献することができます。
受講した学生の声
